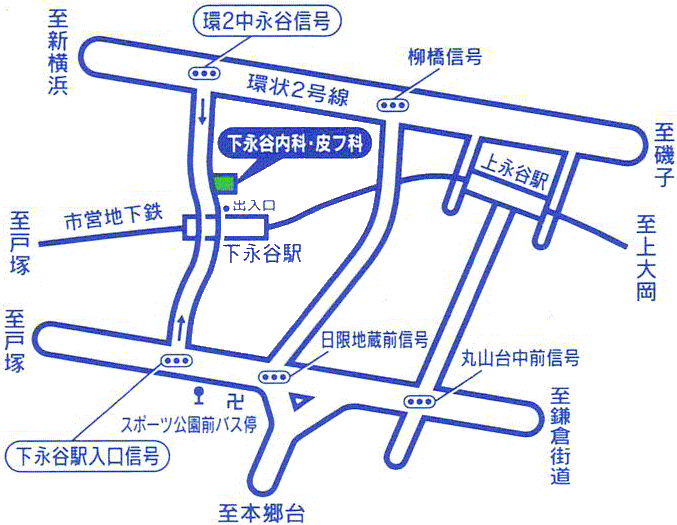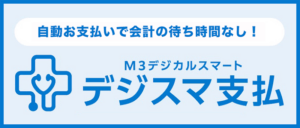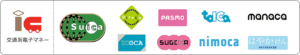腫瘍と免疫
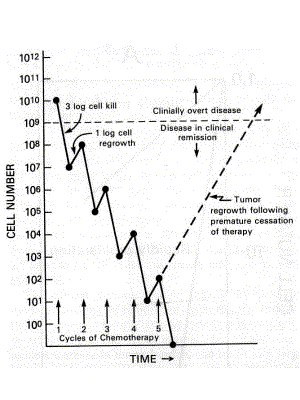
前回の復習
前回、癌細胞の増殖曲線で腫瘍の増殖スピードについて概説しました。今回はこの癌をどう征圧するかを考えてみましょう。
残存腫瘍細胞と化学療法投与の関係
抗がん剤投与を化学療法(Chemotherapy)と呼びます。次に、化学療法が腫瘍細胞にどのように作用するかを説明します。
- 第1回の化学療法
- 3 log cell kill(10^3の腫瘍細胞を殺す効果)により、腫瘍細胞は臨床的に検知不可能なサイズになります。
- 再増殖と次回の化学療法
- 化学療法のダメージから患者が回復する間に、1 log cell regrowth(10^1の腫瘍細胞の再増殖)が起こります。
- その後、第2回の化学療法を行います。
- 繰り返しの化学療法
- 同様に第3回、第4回の化学療法を行うと、腫瘍細胞は10個だけ残る計算になります。
- 最終目標
- 第5回の化学療法で腫瘍細胞が0になることが目標です。
化学療法や放射線療法が失敗する理由
- 宿主細胞への影響
- 腫瘍細胞は宿主細胞の遺伝子の変化であり、元は宿主細胞です。腫瘍を叩けば宿主も叩かれるため、副作用が大きく、大量の薬を使えないのです。
- 抗生物質との違い
- 抗生物質は異なる種の細胞(細菌)を叩くため、副作用が少なく効果が出やすいです。
- 耐性の問題
- 抗がん剤や放射線治療を行うたびに、腫瘍細胞は耐性を強化します。
- 治療効果の限界
- 現在の抗がん剤は3 log cell killの効果がないため、せいぜい腫瘍のサイズを半分にする程度です。これではすべてのがん患者の命を救えません。
分子標的薬の登場
近年、癌治療において分子標的薬が登場し、治療の選択肢が広がりました。
- 分子標的薬とは
- 分子標的薬は、癌細胞の特定の分子構造や機能を標的とする薬剤です。正常細胞に比べて癌細胞に特異的な分子を攻撃することで、癌細胞の増殖や生存を抑制します。
- 代表的な分子標的薬
- HER2阻害薬(トラスツズマブ):HER2陽性乳癌に使用されます。
- EGFR阻害薬(ゲフィチニブ、エルロチニブ):EGFR変異陽性肺癌に使用されます。
- VEGF阻害薬(ベバシズマブ):血管新生を抑制し、腫瘍への血流を減少させます。
- 効果と課題
- 分子標的薬は、特定の癌に対して高い効果を示し、副作用も従来の抗がん剤に比べて少ない場合があります。
- しかし、効果が限定的であるため、すべての患者に有効ではないことや、耐性の発現が問題となります。
免疫チェックポイント阻害剤の登場
免疫チェックポイント阻害剤も癌治療において重要な役割を果たしています。
- 免疫チェックポイント阻害剤とは
- 免疫チェックポイント阻害剤は、免疫系のブレーキを解除し、癌細胞に対する免疫応答を強化する薬剤です。これにより、免疫細胞がより効果的に癌細胞を攻撃できるようになります。
- 代表的な免疫チェックポイント阻害剤
- PD-1阻害剤(ペンブロリズマブ、ニボルマブなど)
- PD-L1阻害剤(アテゾリズマブ、アベルマブなど)
- CTLA-4阻害剤(イピリムマブ)
- 効果と課題
- これらの薬剤は、特定の癌に対して非常に効果的であり、長期生存をもたらすケースもあります。
- しかし、副作用やすべての患者に効果があるわけではないなどの課題も残されています。
最後は免疫力が鍵を握る
- 免疫力の重要性
- 残った100個程度の腫瘍細胞を宿主の免疫力が叩き壊せば、癌から生還できます。
- 若い頃の免疫力
- 若い時には免疫システムが腫瘍細胞を早期に発見し、排除します。
- 研究の進歩の必要性
- 腫瘍細胞と正常細胞の決定的な違いを掴み、それを叩くことができれば、医学史は激変します。しかし、現時点ではこの研究が進んでいません。
- 生活習慣の影響
- 加齢、喫煙、ストレスなどが腫瘍に対する免疫力を低下させます。健康的な生活習慣を維持することが重要です。
現在の治療と今後の展望
- 免疫チェックポイント阻害剤や分子標的薬は今後の癌治療の柱となる可能性があります。
- 個別化医療:患者一人ひとりに適した治療法を見つけるための研究が進んでいます。
- 予防:癌を予防するための生活習慣改善や定期的な検診が重要です。