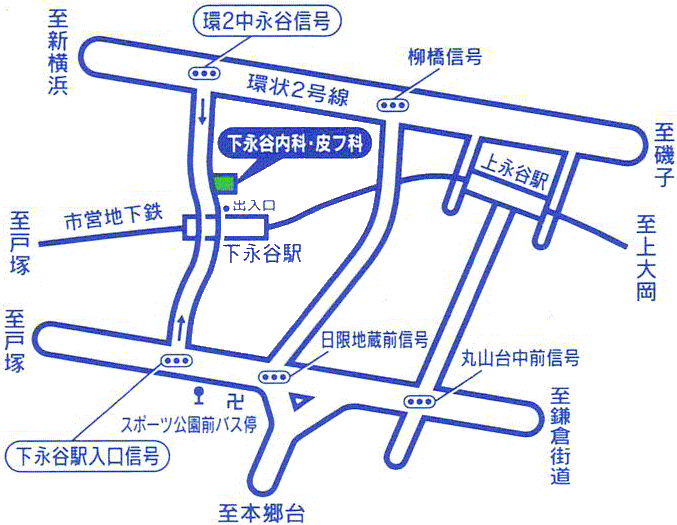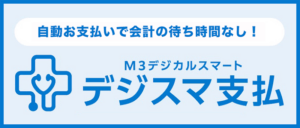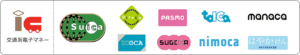尿蛋白
Urinary Protein
基準値
- 定性: 陰性
- 定量: 0.044~0.295 g/日
検査データの読み方
軽度増加
- 定性: 1+~2+ (30~100 mg/dL)
- 定量: 0.5~1.5 g/日 しばしば認める病気:
- 慢性糸球体腎炎
- 糖尿病性腎症
- 高血圧性腎硬化症
時に認める病気:
- 良性蛋白尿 (起立性蛋白尿、熱性蛋白尿など 1 g/日以下であることが多い)
- 重金属や薬剤性尿細管障害
- 間質性腎炎
- Fanconi症候群
どうするか:
- 腎障害をきたしうる全身疾患 (高血圧、糖尿病など) や薬剤の使用歴の検索
- 尿中 NAG、β2-ミクログロブリン測定
- 腎生検
増加
- 定性: 2+~3+ (100~300 mg/dL)
- 定量: 2~3 g/日 しばしば認める病気:
- 慢性糸球体腎炎
- 糖尿病性腎症
- 巣状糸球体硬化症
時に認める病気:
- 腎アミロイドーシス
- 糸球体微小病変 (微小変化群)
どうするか:
- 血尿の有無
- 腎機能検査
- 全身疾患の検索
- 最終的には腎生検による診断に基づき治療方針を立てる
高度増加
- 定性: 3+~4+ (300~1,000 mg/dL)
- 定量: 3.5 g/日以上 しばしば認める病気:
- ネフローゼ症候群
- 微小変化群
- 糖尿病
- 慢性糸球体腎炎 (膜性腎症、膜性増殖性腎炎など)
- 巣状糸球体硬化症
時に認める病気:
- 腎アミロイドーシス
- ループス腎炎
- 紫斑病性腎炎
どうするか:
- 専門家に相談し腎生検を施行し、確定診断し治療方針を立てる
どうして異常値が出たのだろう?
腎臓が障害されている可能性がある:
- 腎臓の組織検査 (腎生検) がないと腎疾患は確定診断が困難。
- 最近の腎生検は安全に行われるようになった。
尿蛋白のタイプ
1) 糸球体性蛋白尿
- 糸球体基底膜でのsize barrier (コラーゲン線維の網目の小孔、半径約70Åといわれている) あるいはcharge barrier (陰性荷電しているプロテオグリカンとラミニン) が障害されて尿中へ蛋白が排泄されたものが尿蛋白として認識される。
2) Selectivity Indexの低下
- 通常は比較的分子量の小さいアルブミンとβ-グロブリンが主であるが、基底膜の破壊が強いとき (膜性増殖性糸球体腎炎、糖尿病、アミロイドーシスなど) には、γ-グロブリンなど大きな蛋白も排泄される。
3) 尿細管障害
- 正常な糸球体からはα1-ミクログロブリンやβ2-ミクログロブリンなど低分子蛋白が排泄され、近位尿細管で再吸収されているが、尿細管障害のときにはこれらの蛋白が大量に尿中に排泄され蛋白尿となる。この場合1.5 g/日以上になることはほとんどない。
4) 良性蛋白尿
- 起立性あるいは熱性などの良性蛋白尿は、1日1 g以上排泄されることはない。早朝尿で蛋白陰性で立位負荷したときにのみ陽性なら、起立性蛋白尿の可能性が大である。